メロンはなぜ桐箱に納めるのか
Eat 7号: パッケージ

この記事は2001年10月に公開されたものです。
日本的パッケージの起源をたどると、どうやら祝儀袋の右上についている六角形の飾り=「熨のし斗」ということになるようだ。今日では袋や包装紙にあらかじめ印刷され、「熨斗袋」「熨斗紙」などと呼ばれているが、もともと熨斗は、それ自身が独立したパッケージだったのである。

折紙に包まれている黄色い短冊状の物は、その名の通り「のし鮑(あわび)」であって、つまり熨斗とは贈り物に付帯された鮑のことに他ならない。
では、なぜ進物に鮑貝を付帯する風習が出来たかというと、一説に進物が不祝儀のものでない証に生臭物を添えたからとも、また鮑に邪気を祓う属性があるからとも説明される。しかし、前者に従うなら熨斗は仏教の反作用的影響を受けて発生したということになってしまうし、後者の邪気を祓うという考え方も、南方熊楠が指摘しているように鮑の真珠質から反射する光線の魔力に感応したもので、言うまでもなくこれは貝殻を対象とした信仰である。

鮑が、仏教伝来以前から神饌として欠くべからざる食材であったこと、また、その身を薄く削ぎ、生乾きのうちに伸ばして乾し上げたのし鮑が極めて重要な保存食でもあったこと等を鑑みれば、熨斗に対して無理矢理呪術的説明を施すよりも、神饌をーー否、むしろ御神酒(おみき)を奉る際につまみとして添えた、と解釈する方が素直ではないだろうか。事実、のし鮑は酒肴としても絶品で、その上品な旨味は、到底スルメやカワハギなど他の干物の及ぶところではない。
そもそも、日本人には食べ物なしに飲料を摂ることを忌むきらいがあって、現在でも、居酒屋でお酒を注文すると頼みもしないのに突出しが来るし、お客にお茶しか出さないいわゆる空茶(からちゃ)を、もてなす側の怠慢だと考える習俗も場所によっては残っている。
テクストが存在しない神道では、本来神饌にまつわる杓子定規な規範もないのだが、基本的には人が食べて旨いと思うものは神も喜ぶという考え方に根差している。故に、神に御神酒を奉る際にも、人に対するのと同様の精神構造が機能した可能性はないとはいえない。
「ただお決まりのものだけ差し上げるのもぶっきらぼうですので、ちょっとのし鮑を添えておきます。口さみしい時にでも噛んで下さい」。そんな、いかにも古日本人的発想が、進物に添えられる熨斗の発生と、関連しているように思えてならないのである。

鎌倉時代の説話集『古今著聞集』には、贈られてきた瓜を怪しく思った藤原道長が、陰陽師に吉凶を占わせるくだりがある。古代人は、物には所有者の魂が宿ると考えていたから、みだりに他人の所有物に触れることをしなかったのである。
しかし、熨斗を添える風習が発生したことにより、進物は贈り物であることを明示出来るようになった。熨斗がついてさえあれば、そのモノは所有者不在状態にあるのだから、第三者が触っても安心という理屈である。
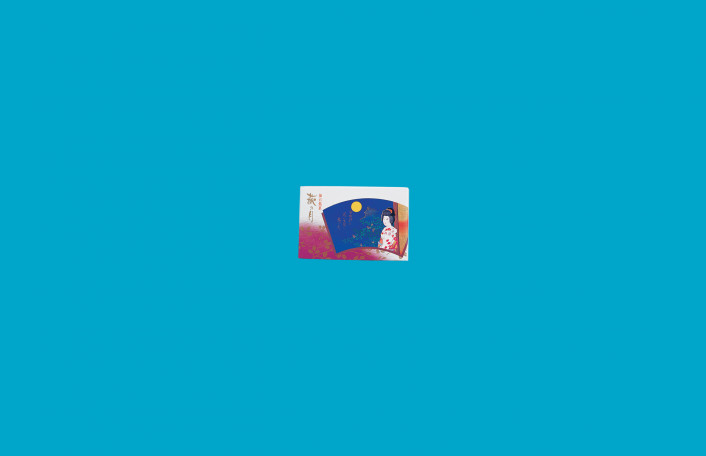
モノのやりとりに「包む」ことが必要な理由
かくて、にわかに包むというアクションが重要視されたであろうことは想像に難くない。
このように贈り物は、余人の手垢のついていない初(うぶ)な状態であることが望ましいわけで、贈り主の魂は次の所有者が手にするまでに祓われなければならない。それには、モノを特定の空間に篭らせる、すなわち包装するのが手っ取り早い対処法である。
竹の節でも、箱でも、袋でも、風呂敷でも、中が空洞で外界から独立した空間には、子宮としての属性が認められている。そこに篭るという行為は、象徴的に過去を清算し、生まれ変る儀式に他ならない。天界で罪を犯した天人がかぐや姫となって竹の中から誕生したのは、その好例といえよう。

つまり包装することによって所有権がサラな状態を演出するわけで、今ではだいぶ廃れてしまったが、日本人が売買以外で金銭のやりとりをする際に裸銭を嫌うのはこの考えに拠るものだろう。たとえ小遣いやチップのような小銭であっても熨斗のついたぽち袋に入れ、それがなければ半紙に包むという風習は、心付けなどというあやふやな贈り物に漂う前所有者の執念を、贈り主自ら払拭する気配りなのである。この慣習はなにも改まった進物のみのものではなくて、例えばお惣菜を隣にお裾分けする時は鉢に布巾をかけてゆく、子供にお菓子をやる際は半紙をおひねりにして与える、などという按配に生活に密着していた。
このように、包むという属性が重視された結果、次第に熨斗からは食べるという属性が消えてしまう。本来のし鮑であったものが黄色い合成樹脂の短冊に代り、また単に包装紙に印刷された模様というかたちに形式化し、つまり俗化してゆくのである。
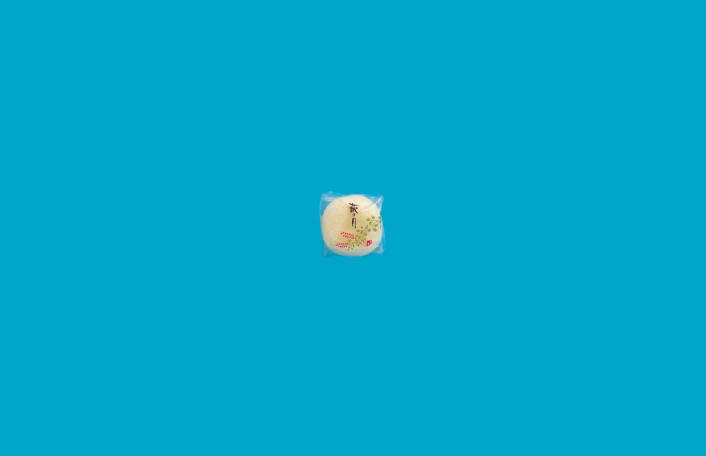
さて、もうおわかりであろう。包装が過剰に傾く構造は所有権の所在演出に起因している。包装は、それが過剰であればあるほど、贈り主のへりくだりの意を表わすのだから、むしろ贈る側の心情としては進物の中身よりも贈ったという行為の方が大切なわけで、メロンは桐箱に入れられて初めて意義を持つのである。してみれば過剰包装は進物の宿命ではあるまいか。うやうやしく届けられた桐箱に、絹に包まれて収まったマスクメロン……なんだか道長の瓜が千年の時を経た姿に見えなくもない。
こうした象徴的パラドクスを手玉に取る奴がいつの世にもいるもので、江戸中期の幕府老中田沼意次にあろうことか数尾の鱚(キス)を贈った者があった。前近代では役得は当り前、飛ぶ鳥を落とす権力者になんたる貧弱な贈り物かと思うも束の間、薬味の柚の皮剥きに名工の手になる小柄(こづか)が添えられていることに気づくという仕組みである。どうせ贈ることに意義があるのなら、包装の方にウェートを置いてしまえというこれは、中身と包装の主従を逆転させた遊戯。贈り物という文化が、遊びと美というエッセンスを得て爛熟した証、ともいえるだろう。
「日本のコンビニで包装を拒否すると、それでもテープを貼られてしまう。」と、ある外国の人が不思議がって居られたが、たとえテープ一片とはいえ、篭り=祓い=所有放棄という構造を踏まえなくてはモノの移動はかなわない。それは、この国に掛けられた呪術が日本人も知らぬ間に形式化し、常識化した名残に他ならないのである。
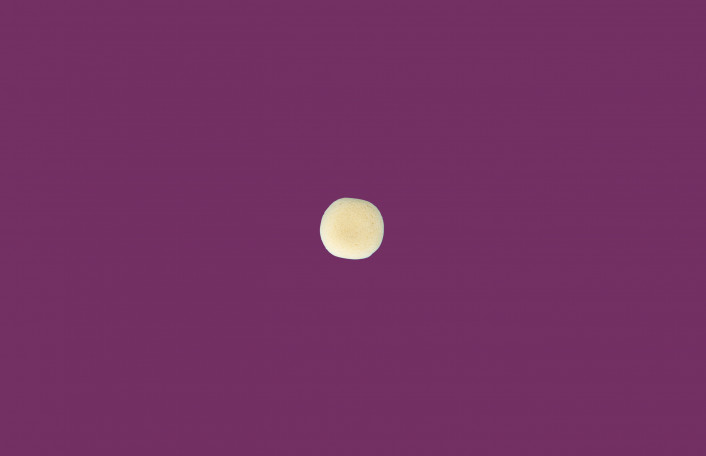
文/高山宗東 写真/森山あゆみ





